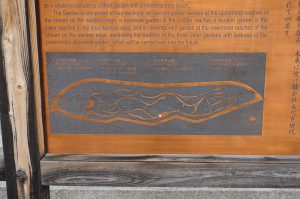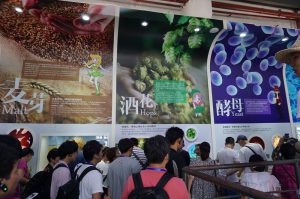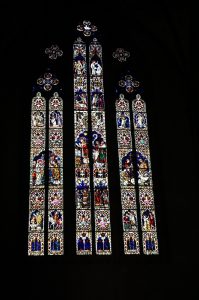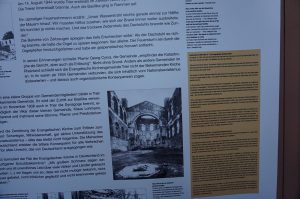11月17日のソウルでの結婚式に出席した後、教え子の陳さんの案内で朝鮮王朝の宮殿「景福宮」の見学と、近くの「仁寺洞通り」の散策に行った。
披露宴会場から「景福宮」まで、交通渋滞のあり車で1時間以上もかかった。車を「景福宮」の地下の駐車場入れ、「景福宮」に。この時期入場の締め切り時間が16時で、ぎりぎり入れた。
「景福宮」は1395年に建国された朝鮮王朝の宮殿。ソウルのシンボル北岳山の前に宮殿の場所が決められた。宮殿北側には韓国大統領府「青瓦台」、正門の「光化門」は、韓国の政治と経済の中心となっている「世宗大路」に面する。
「景福宮」は文禄の役(1592年)で焼失したが、1867年に建て直された。しかし、朝鮮物産共進会(日本の朝鮮統治の成果を示し、朝鮮の更なる産業の発展を図るために開催された博覧会)開催の名目で宮殿の多くの建物が取り壊されてしまった。1990年から復元事業が始まり、本来の「景福宮」の姿を取り戻しつつある状況である。
境内は多くの観光客で賑わっていた。多くの観光客が、レンタルした韓国伝統の韓服を身に着け、朝鮮王朝時代へのタイムスリップを楽しんでいる。(韓服を着用した観光客は入場は無料)以下、駆け足で見学した「景福宮」の主要な建物を紹介する。
1.光化門
景福宮の正門。朝鮮戦争の時に焼失したが、1968年2月、復元された。
中央の門が光化門
勤政門をくぐると勤政殿
2)勤政殿
景福宮の正殿で、最も華やかで王の権威を示す建物。ここでは、王の即位の礼、文官、武官が集まる朝会、外国からの使臣との接見公式など、国家儀式が行われた。宮殿内は1階と2階が吹き抜け構造で、天井まで見渡せ、天井には様々な文様が鮮やかに描かれている。
勤政殿に繋がる石畳。
勤政殿の内部
勤政殿の天井の鮮やかな文様
3)思政楼
王の執務室。ここで日常の政治活動が行われた。現在の思政楼は1867年に再建されたもの。
思政門をくぐると思政楼に
4)康寧殿
王が日常生活を送った宮殿。現在の宮殿は1995年に復元されたもの。
6)慶会楼
池に囲まれた慶会楼
勤政殿まえの石畳の広場
韓服を着用した外国人観光客
夕方5時が閉門ということで、ここで宮殿の見学は終了。
光化門を出て左折し、仁寺洞(キョンボックン)通りの散策に。
景福宮境内から光化門をくぐって外に
光化門をバックに「世宗大路」を望む
景福宮の東の端にある「東十字閣」(右)とその後ろには奇抜なデザインのTwin Tree Tower
仁寺洞(キョンボックン)通りの賑わい。通りには、伝統工芸品、絵画道具の店、ギャラリー、骨董店、喫茶店が、一歩路地に入ると、昔ながらの韓家を改造した飲み屋、レストランが並んでいる。
仁寺洞通りから辻を入ると昔ながらの街並みが
仁寺洞通りの喫茶店(3階)からの眺め
仁寺洞通り入口に点灯された、韓国式提灯
この仁寺洞通り、整備が進み、とみに観光客が集まるスポットとなっている。特に若い人に人気がある。