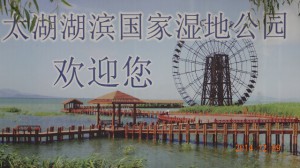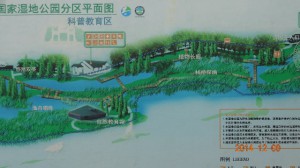3月23日から27日に、ベトナム・ハノイに出張していました。
ハノイには過去15年間、毎年1-2回、訪れていますが、訪問の度に街が大きく変貌するのに驚いてきました。今回の訪問ではこのほど完成したノイバイ国際空港の国際線専用ターミナルと同市中心部からの交通アクセスを改善する橋、高速道路に殊の外驚かされました。
2012年2月から日本の技術活用型の円借款で行われていた、ハノイ・ノイバイ国際空港・第二旅客ターミナルを新築する建設工事が完成し、この2月から運用が開始。この工事、日本の大成建設と地元のビナコネックスのJVで、総工費761億円(78%が円借款)をかけて行われました。これまでのノイバイ国際空港・旅客ターミナルは国内線専用のターミナルとして使用されることです。ターミナルはオープンして一か月余りということで全てピカピカ。これまで、多くの東南アジアの空港ターミナルを見てきましたが、その多くは、外見は立派なものの、ディーテイルに問題がありました。新装なったノイバイ国際空港・第二旅客ターミナルは日本の技術を活用し、大成建設が主導したこともあり仕上がり状態は日本基準。エアコンの効いたボーディグブリッジは日本と同じもの。歩く歩道、エスカレータ、ターンテーブルはFUJITECでこれまた日本と全く一緒。ベトナムの空港では預けた手荷物がターンテーブルから出てくるのにひどい時は30分以上かかっていたのが、イライラすることなく10分程度で出てきました。日本への帰国時のチェックインも、以前は30分待ちも当たり前であったのが、日本並みの待ち時間に。入国審査、手荷物検査もこれまでになくスムース。まさに、これからのベトナムの経済発展を象徴するターミナルになりました。
駐車場から第二旅客ターミナル一階のエントランスに向かう
第二旅客ターミナル一階には綺麗な水の池を配置
発ロビーの様子(天井は関空や福岡国際空港に似ている)
開放的な免税店
ムービングウォーク(FUJITEC製)で出発ゲートに向かう
21番ゲート付近の様子
これに加えて、ノイバイ国際空港と市内を結ぶ新しい連絡道路とそれを可能にする紅河にかかるニャツタン橋(総事業費は1070億円で、このうち68%が円借款)も同時に完成。これまで、ハノイ市中心部から空港に向かう道路は1本しかなく、市内から空港まで1時間あまりもかかっていたのが、30-40分と大幅に短縮されました。これまでの空港までの連絡道路は、一見自動車専用の高速道路に見えるものの、バイクも走り、一般道路も横断していてこの上のない危険な道路でした。これが、片側3-4車線、最高速度が80㎞の自動車専用道路となり、道路の照明、交通表示も分かりやすくなりました。夜間水銀ランプで証明されたこの道路を走っていると、どこか先進国の高速道路と錯覚してしまいます。ニャッタン橋(愛称日越友好橋)は東南アジア最大級の斜張橋で、5個のひし形の橋脚と220本のケーブルで支えられています。まだ橋脚やケーブルのイルミネーションはされていませんが、この橋がイルミネーションされれば、ハノイ観光の名所になること間違いなしです。
紅河にかかるニャッタン橋(在ベトナム大使館HPから引用)